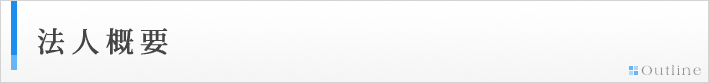- トップページ
- 法人概要
概要
| 名称 | 一般社団法人医療介護チェーン本部 |
|---|---|
| 住所 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-2-14 日本橋KNビル4階 TEL:03-5201-3575 MAIL:info@medical-chain.or.jp HP:https://www.medical-chain.or.jp/ |
| 高知事務所 | 〒780-0870 高知県高知市本町5-6-35 つちばしビル3階 |
| 法人の公告方法 | 官報に掲載する方法により行う。 |
| 法人設立の年月日 | 平成23年7月15日 |
| 役員に関する事項 | 代表理事 吉岡隆興 |